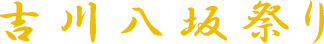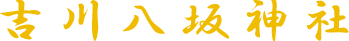四百年の歴史を持つ吉川八坂祭り。独特の吉川甚句の節に合わせ神輿を担ぎます。
俗称を天王様と言い、商売繁盛、五穀豊穣、悪疫退散を祈念し、平沼の氏子が奉仕する吉川八坂神社の祭儀です。
始まりは、1602年(慶長七壬寅年)に吉川宿が分村(上宿・中宿・下宿)されたときに初代の神輿が製作された時。現在の神輿は二代目、1853年(嘉永六癸丑年)に再築されたもので、芳川神社境内にある八坂神社の御神体として祀られています。
一つの御神輿が町内各地を巡幸していた頃は、集落境で御輿の受け渡しを行っていました。その際、なかなか渡したくない側と、早く受けたい側と、渡し渋りが続き、渡御が明け方近くまで繰り広げられることもまれではなかったそうです。
御神体の各町渡御の儀式(受け渡し)は別の形で現在も伝えられていますが、二代目御神輿は、長らく祭儀の際に町内各地を巡幸し、百四十余年の年月を経て、傷みがはげしくなったため現在は各町の御輿が渡御します。
この大神輿(二代目御神輿)を御神輿殿から出し、その前で各町内毎の神輿を自分の町内に祭り込み繰り出させるための儀式(神事)が厳粛に行われます。この儀式(朝祭り)が終わらないと、各町内(現在は十町)の神輿が自己の町内に祭り込む事はできません。
暴れ神輿・喧嘩神輿と呼ばれるのは、神輿を頭上高く差し上げ、更に上に投げ(サシ)揚げることから。江戸時代から大正末期にかけて、平沼地区は中川を中心とした水運の中継点として河岸場が栄えており、河岸に働く船頭達の力自慢が発祥とされています。
しかしながら、不思議なことにトラブルや怪我人等の犠牲者が出ないめでたいお祭りとしても知られています。
昔、祭禮は七月九日の早朝から十五日まで実施されていました。その後、十三日から十五日までとなり、近年では十五日直近の土日に執り行われています。二日目(日曜)の夕刻には平沼地区十町から九基の神輿が集まり、暴れ神輿の競演がイチョウ通りにて行われます。
この暴れ神輿の競演は、高張り提灯に先導された各町の神輿が、約五百米の区間に九基も繰り出され、競い合って祭る(投げ揚げる)もので、まさに圧巻の一言です。

天正三乙亥年三月十五日(1575年)、北条氏執権梁田持助より吉川住人戸張将藍が吉川村平沼の里に物品を商う市場を開く御朱印状を戴き、翌十六日より市を開いた。
その市場の守護神として京都八坂神社より分御魂を御奉祀。
御祭神は素戔嗚尊(スサノオノミコト)で商売繁盛、悪病除の神様。
古くから、町内には新たに収穫したキュウリを八坂神社に奉納するならわしがある。
初代の御神輿は慶長七壬寅年(1602年)に製作された。
現物は二代目で、嘉永六癸丑年(1853年)に再築されたもの。
祭儀は平沼の氏子が御奉仕し、古くは七月九日より十五日までの七日間執り行われていた。
現在は十三日が宵宮、十四、十五の両日御神幸祭を執り行ない、十 五日には御神体が町内各地を渡御する。(尚、交通事情等により昭和57年より十五日の直近の土・日に御神輿の渡御、山車の巡行を行っている)
神社合祀の国の指令に基づき、明治四十五年に芳川神社(当時は、諏訪神社)境内に移され、現在に至る。
(以上、芳川神社「御由緒」を参考にしました。)
素戔嗚尊(スサノヲの命)
記紀に登場する神。伊弉諾尊の末っ子で、天照大神、月読命と共に三貴子(三貴神)の一人。高天原で大暴れをし、天岩戸の事件へと。
高天原を追われ地上に降り、八俣大蛇を退治。三種の神器の一つである草薙剣をその尾から取り出す話も有名。その時救った櫛名田比売を妻に迎え、出雲の地で暮らす。その後、母・伊弉冉尊の住む黄泉の国へと向かう。
その子孫が大国主命であり、娘・須勢理毘売との結婚に対し試練を与えるが、大国主命の国造りに助言をする。
このように、天上・地上・黄泉の国と三箇所で全く違った顔を見せます。八俣大蛇を退治したことや、高天原での粗暴ぶり等から荒々しい程の力で災いを祓う悪疫退散の神とされ、八坂神社や氷川神社などの御祭神となっています。
素戔嗚尊を始め、御霊系の神社で夏祭りが盛んで派手なのは、夏に向かい疫病が流行する季節に、それを封じ込めることを目的とするためです。(併せて、五穀豊穣を願います)
ちなみに、芳川神社(諏訪神社)の御祭神は、建御名方命。大国主命の次男であり、国譲りの際に不服として、建御雷神に力比べ(戦い)を挑み、敗退して諏訪の地に落ち延びました。この建御雷神は鹿島神宮の御祭神です。また、このときに同道していたのが経津主神(香取神宮の御祭神)です。
八坂祭に限らず、素戔嗚尊を御祭神とする神社でのお祭りが天王様と呼ばれるのは、素戔嗚尊が祇園精舎の守護神(仏教神)である牛頭天王に擬せられる、或いは、合祀されていたためと考えられます。